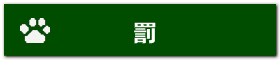「叱らなくてもきちんと育ったたくさんの実例」や、「叱って、更に悪くなったたくさんの実例」を並べ立てて、
叱ることを不要だと言い出す人がいます。
そもそも、罰はいけないと言い出すこと自体が不思議でなりません。
悪事を制するものが罰なのです。
本当にいけないものであるなら、なぜ私たちの周りにこれほど罰が溢れているのでしょうか。
スキナーの提唱する「罰なき社会」とは「罪が不問とされる社会」に他なりません。
罰の無い社会であれば、殺人、暴行、窃盗その他、何でも自由に行なっても、何ら咎められることはないし、
それらを行なったことを理由に嫌な目に合うことはないのです。
しかし、行なえるということは、同時に行なわれるということです。 悪いことをしたから罰を受けるのです。
悪いことをした人が、おとがめなしなのであれば、罰を受ける者が行なった行為による、被害者の権利は どのように保護されるのでしょうか。
悪さしたもの勝ちの世の中です。周囲の人に迷惑をかけているから叱るのです。
これを叱ることがいけないのであれば、迷惑を受けている人は耐えて我慢するしかないのでしょうか。
手間と時間をかけ、相手と対等の立場に立って、説得して合意を得なければならないのでしょうか。
「罰はいけないもの」という風潮がまねく、大きな弊害についても認識する必要があるでしょう。
そうした風潮は、人前で叱ることを躊躇させてしまいます。
個体による必要性の差もきちんと考慮しなければなりません。
おだやかな刺激の少ない環境で育った子と、がさつな刺激の多い環境で育った子とでは、または、
感受性の強い子と弱い子とでは、与えられた同じ叱責でも与える影響は全く違います。
活動性や新奇性、臆病度合いなどによって、自発的行動そのものも違います。
一度も叩かれたこともなくきちんと育った子はたくさんいます。
そもそも、環境やその子の個性によって、叱ることが必要なような行動をおこさない子もいます。
けれどもそれは、叱る必要のない子もいる、叩かなくてもわかる子もたくさんいるということであって、
それが叱ることはいけないことだ、不要なことだという理論にはなりません。
そして同時に、手のかからない子が良い子で、 いくら言ってもきかない、叩かないという事をきかない子が悪い子というわけでもありません。 手のかからない子、聞き分けのよい子、素直な子というのは、いるものです。
という事は、同時にその全く逆の子もいるということです。
褒めるだけで一度も叱らずに上手に育った例はたくさんあるから、という論法についても、 はたしてその方法が、良かったのか、その子の素質が、叱るべく行動を起こさないものであったのかは不明です。
個性の尊重だの、個性に合わせた教え方だのと言いながら、叱ることについては全てだめだと言われると、
叱って教えることが私の個性だ、と言いたくなります。
・悪事、怠惰の助長
・弁別条件付けによる効果の低減(人前で叱らなくなれば、人前では叱られないと思う。)
・隠蔽体質の助長
・機をとらえた指導ができない
・罰技能、向上の機会の喪失
・抑止効果さえをも奪う
・容認が既得権につながり、逆切れを生む
|