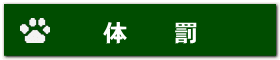「体罰」は、いいのか、いけないのかについて考えてみましょう。
訓練における体罰の是非については、大きく意見の分かれる問題ですが、著書の中で体罰を使ってはいけないと
書いている訓練士で、体罰を用いない訓練士を見た事がありません。
訓練士という職業が、愛犬家相手の客商売という側面を考えれば仕方がないのかもしれませんが、 愛犬をきちんとしつけようと思ってその本を読む方に対して、何とも無責任な気がします。
どなたにしても自分の犬は可愛くてたまらないし、できるならば、叱らずに育ててあげたいと思うはずです。
「旧来の、軍用犬の訓練のように犬を叩いて叱って、犬は怖いから言う事をきくといった教え方ではなく、
愛犬の良いところを見つけ、個性を伸ばしてあげて、犬と一緒に遊びながら、ほめて教えることが大切です。」 そんなキャッチコピーを見れば、誰もがそちらの訓練所を選ぶでしょう。
もちろんその方法でうまく行く場合も多くあります。
しかし、十人十色といわれる様に、人それぞれに性格があり、それ同様に犬にも性格があります。
飼い主と愛犬との組み合わせによる相性によっては、犬が小さい内に、相当厳格に主従関係をたたき込んでおかないと、将来手に負えない犬になってしまう場合もあります。
私は、体罰は、犬によって、あるいは、場合によっては絶対に必要であると考えています。
ただし体罰は両刃の剣である事を念頭に置いて下さい。
誤った体罰は、効果が無いのでは無く、逆効果である事を心得ていて下さい。
しかし、そもそも、体罰とは何でしょうか。
簡単に言えば、お尻を叩くことは、全てにおいて体罰なのでしょうか。
例えば、何かの行動をさせたい時に、相手にその行動を惹き起させるための刺激としての殴打と、相手がそれを
しなかった時のお仕置きとしての殴打とを、同一には論じられません。
例えば、同じに「お尻を叩く事」であっても、「座れ」を教えるのであれば、犬にその行動を惹き起させるための刺激と認められますが、「立姿」を教える場合には、そうはなりません。
「殴打」という、犬にとって不快な刺激を回避しようとして、犬は、反射的にお尻を下に下げるのです。
このように、犬に与える不快な刺激から、犬がそれを避けるために行なうもっとも自然な行動が、人間が教えたい行動である場合にのみに限られるべきでしょう。
当然に、犬の性格を踏まえて、強弱を加減しなければなりません。
犬に恐怖感を与えるほどの強さであれば、犬は、反射的に噛みついたり、逃走したりといった行動に走ってしまうことがあります。 また体罰否定論者の中には、水を掛ける、大きな音で驚かすなどの方法を推奨している場合があります。
しかし人間的な感覚からすれば、それほどかわいそうに思えない方法であっても、 犬に効果があるとするなら、
それ相応のダメージがあるわけです。 要は、罰を与える側の罪悪感の違いであって、犬にとって、不快である事は同じなのです。 逆に言えば、罪悪感のないままに、犬に不快を与え続ける方が残酷なのかも知れません。
また、無視するという方法を推奨する人も多いのですが、人間社会で考えれば、無視するという対応は、
いわゆる、「シカト」と呼ばれる、イジメの第一手段でもあり、最も陰湿なものでもあります。
また、よく、ネズミに電気ショックを与えての実験結果を基に、罰の罪を説かれることがありますが、
特定の条件における結果を、そのまま全てに当てはめることは、あまりにも乱暴すぎます。
なぜならば、罰の種類や、強弱だけが、結果を左右するのではないのです。
先の例で言えば、ネズミがどういった行動をとった時に、電気ショックが与えられる設定になっているのか、
によって、その結果は全く異なります。つまり、ネズミ自身が、自分の行動次第で避けられるか否かによって、
また、どう行動すれば避けられるのかを理解しえるか否かによって、結果は全く違ってくるのです。
例えばわが国にも、罰として、死刑の制度があります。
だからといって、国民が常に死刑の恐怖におびえながら生活しているわけではありません。
何時襲ってくるかわからない恐怖と、自分の行動によって容易に避けることができるとわかっている恐怖とでは、全く違うのです。 もし罰を使うのであれば、「どうすれば避ける事ができるかを、相手に早く理解させる事」に 充分な配慮をするべきでしょう。
また、道端で出会った見知らぬ人に叩かれることと、学校の先生に叩かれるのとでは、あるいは同じに学校の
先生でも、嫌いな先生に叩かれるのと、敬愛する先生に叩かれるのでは、受けとめ方はまるで違います。
このように、罰の多くは相手との関係性によって、その効果も弊害も大きく違う結果をもたらします。
要は、体罰を与える側と与えられる側の、精神的信頼関係や、それ以外の体罰に至るまでの背景などを無視して、一概に可否を述べることは、適切ではないでしょう。 |