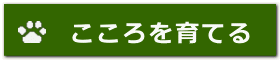犬の起源については諸説があります。
人類が他の動物とは異なる生活圏を築き始めた時に、人類に付いてきたのが犬なのでしょう。
イヌは、野生を捨てて犬になったとも考えられます。
イヌという動物がもつ、最高の能力は何でしょうか。
それは、人間の要求に応じて変化する能力であると私は思っています。
人間がどのように品種改良を図ろうとも、犬以外の動物で、これほど多様な変化を見せる動物はありません。
犬を飼うことを人間のエゴだと考える向きもあるようですが、人と犬とは共存共益の関係です。
人間が犬を保護するのは、犬が弱い立場だからではなく、人にとって必要な存在だからではないでしょうか。
やれ愛護だの保護だと騒ぐ人ほど、この本質を理解していないように思えてなりません。
秩序や安定を求めるくせに、主従関係、上下関係と聞くと途端に嫌悪感を示す人が多くいます。
よっぽど上長に恵まれてこなかったのでしょう。 我が家の先祖は、徳川家15代に亘ってその身の回りの
お世話をして仕えてきたと聞けば、それなりの由緒を感じます。私の気持ちにおいては、仕えることに対して、
屈辱という発想はなく、むしろ有能な者に仕えることは誇りにさえ思えるのですが、いかがなものでしょうか。
私は、相手の能力に応じた処遇こそが、本当の優しさであると考えています。人間においても同じです。
会社員の全てが社長になりたいわけではありませんし、それに適した能力を身に付けているわけではありません。
能力のない者を社長にすることは、会社にとってもその人にとっても不幸なことです。
また、能力を引き出し伸ばすことはいくらでも可能でしょうが、それには能力が潜在していることが前提です。
無いものは、引き出すことも伸ばすこともできません。潜在能力の有無の見極めが重要です。
また、能力以上のものを求めることは、相手の負担にしかなりません。
そして重要視されない能力は、繁殖において選択されないために代を経て消滅することを知っておくとともに、
成育過程で必要とされない能力は、成長における発達と共に退化し消滅することや、
能力を伸ばすには、それに適した時期があることを忘れてはなりません。
能力は、トレーニングされることによって開花するのです。
ここでいうところの能力というのは、頭の良さだけをいうのではありません。
嗅覚・味覚・触覚・聴覚・視覚などのいわゆる五感を担う五官の機能能力や従順性や協調性などといった
あらゆるものをいいます。
例えばイヌの特筆すべき能力の一つに、「他種であるヒトとともに協調行動をとることができる能力」あります。
使役動物として、作業能力と共に従順性を求められてきたからこそ、人類の最良の伴侶としての今日の犬が
作り上げられてきたのです。
何千年の人類との歴史の中で、人為的選択交配により、イヌは畜犬としてあらゆる改良が行なわれてきました。
イヌの特性としてまず挙げられることは非常に優れた環境適応能力をもつことです。
より人間の求める姿態や能力を身につけることにより、いっそうに人間に必要とされることによって、
イヌという種の存続と同時に現在の地位を獲得したのです。
おそらくこれからも非常な長期間、すなわち歴史的な歳月において、改良が重ねられていくことでしょう。
ここで重要なことは、家畜化という人間のエゴが現在の犬を作り上げてきたという事実です。
これを否定するのであれば私たちは、現在のような食糧供給を受けることは不可能になります。
怠け心が文明を発達させてきたのです。
苦情がサービスを向上させ、同様に人間のエゴが家畜の品種改良を促してきたのです。
「足るを知ること」が幸せの第一歩と言いつつ、満足が成長を止める事も事実です。
「時代の流れ」や「風潮」あるいは「流行」に左右されてはならないものがあります。
行き過ぎた動物愛護の風潮は、必ずやイヌの稟性の低下を招きます。
終生の生命と生活の保障を受け、食料の確保はもちろん、外敵の心配もなく全てに保護されていること自体が
反自然なことなのです。
その上に一切の嫌悪刺激を受けることなく成長したのであれば、その内面は、もはや動物ではなく、
動くガラス細工のようなものでしょう。
「うちの犬はそんなことはありません。」そのように言い出す人がたくさんいると思います。
しかし、それこそそれは良い犬に巡り合ってきたおかげという話です。
もっと端的に言えば、人間との共存を目的に、人間に対する親和性や服従性を持たない犬を排除して繁殖を重ねてきた、先人の英知と努力の恩恵に浴しているのです。
環境への適応は、繁殖における世代間、および、成長や発達という個体内において行われます。
種の進化は、遺伝的形質の突然変異・自然選択・遺伝的浮動により、個体においては後天的形質の獲得と
消失により行なわれます。
良いことか悪いことかは私にはわかりませんが、地球において人類が全ての動物を支配しているのです。
犬と言う動物は、そうした人間のエゴが作り上げた産物なのです。
動物愛護という美化された言葉の元で、一方的な愛情や表面的な優しさだけで犬が飼養され、
繁殖をされるようになったなら、犬の持つ服従心、従順性や協調性、あるいは作業欲といった能力は、
必要とされない能力として次第に失われていくことでしょう。
それゆえに、オヤツを用いたトレーニングに対し、私は賛成できないのです。
|
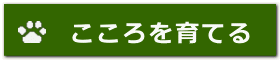
![]() こころを育てる
こころを育てる